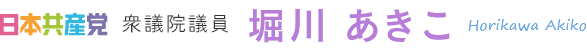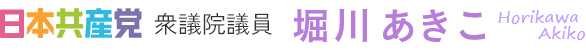国会質問
国会質問


日本共産党の堀川あきこ議員は5月30日の衆院東日本大震災復興・防災・災害対策特別委員会で、能登半島地震で高齢者施設や障害者施設からやむを得ず広域避難した被災者が望めば元の地域に戻れるようにすることは生活再建にとって不可欠だと指摘しました。
被災した能登6市町の高齢者施設のうち再開未定が11、廃止が1(3月17日時点)で、障害者施設では再開予定が2、廃止が6施設(4月末時点)にとどまっています。堀川氏は、施設が再開できない原因がどこにあるのか、職員がどの程度復帰し、被災者がどの程度施設や地域に戻ってきているのかを政府として把握し、具体的な手だてをとるよう強く求めました。
堀川氏は、福祉関係施設の再建には、建物だけでなく必要な資機材や職員の復帰が不可欠で、それらは生業(なりわい)の再建と地域の再生にもつながっていくと強調。坂井学防災担当相は「(現状は)医療や福祉のサービスを提供できる環境がなければ戻りたくても戻れない」として、堀川氏の指摘は「すごく大事なことだ」として、「高齢者施設等の再開は地域の復興のためには重要」だと答弁しました。
(しんぶん赤旗2025年6月4日付掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。今日は、能登半島地震の被災地復興にとって重要な課題である医療、福祉関係の再建について質問をしたいと思います。
先日、珠洲市を訪問してきまして、副市長さんにお話を聞きました。元々珠洲市に七つあったデイサービスセンターの再建についてお話を聞いたんですけれども、見通しの持てない事業所もありながら、地域の利用者のニーズに何とか応えようということで奮闘されておられました。
被災したデイサービスセンターの整備を進めておられたんですけれども、一千万、千五百万規模の工事というのが、事業者も不足している中で、なかなか受けてもらえないということで、三度目の入札でやっと決まったというふうなお話でした。また、職員の確保についても、お子さんや御家族の関係で珠洲を離れざるを得ない職員の方もいらっしゃって、苦労しているというふうなお話でした。
災対法の参考人で来ていただいた障害者支援団体のJDFの大野参考人からは、施設が復旧をしても職員が戻ってこずに、他府県から支援スタッフが職員の穴を埋めている状況だ、元々JDFは三月までの支援だったんだけれども、それを延長して九月末までとしている、ただ、職員が戻ってくるというふうな見通しがなかなか持てなくて、地元に自分たちの支援の活動を引き継いでいくイメージが、これまでのどの被災地よりも持てないというふうなお話をしていただきました。
一年半たって、こうした状況が能登にあるということで、行政はどう対応していくのかということが問われていると思います。
まずお聞きしたいのが、能登半島地震での高齢者施設、障害者施設の被災状況、一年と半年がたとうとしている今、再開の状況はどうなっているか、どうでしょうか。 済みません、ちょっと質問の順番を変えました。申し訳ないです。
吉田政府参考人 お答え申し上げます。昨年の能登半島地震によりまして被災した珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町の能登地域六市町における復旧状況でございますけれども、石川県に確認をいたしましたところ、高齢者施設につきましては、令和七年三月十七日時点で、被災前の施設の数が九十二ございました。これに対しまして、再開した施設も含めまして現在運営中の施設が八十、また、今後再開予定、未定の施設が十一、廃止となった施設が一と伺っております。
あわせまして、障害者施設の復旧状況について、こちらも石川県に確認をいたしましたところ、令和七年四月末時点で、被災前の施設の数が四十六ございました。これに対しまして、再開をした施設を含めまして運営中の施設が三十八、今後再開予定の施設が二、廃止となった施設が六と伺っております。
堀川委員 済みません、続いて厚労省にお尋ねしたいんですけれども、その再開に至っていない事業所が何につまずいているのか、政府は把握する必要があると思いますし、具体的な手だてを取るべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
吉田政府参考人 能登半島地震で被災した要介護者や障害者の方々が希望する地域で安心して暮らすためには、地域で必要となる介護や障害福祉サービスが確保されることが重要であると認識をしております。
このため、厚生労働省では、令和五年度予備費及び令和六年度補正予算におきまして、被災した介護、障害者施設等の復旧を支援するための予算を確保しまして、施設の被害状況の確認と併せまして、再開に向けた課題の把握を行っているところでございます。
再開に至らない理由につきましてですが、災害復旧が途上であるということに加えまして、利用者が避難先での生活の継続を選択したこと等によりまして介護や障害福祉サービスの需要が減少していること、また、これに伴いまして、介護、障害福祉人材の必要数が減少していることなどが複合的に関連しているものと考えられます。
能登半島地震で被災した利用者が希望する地域で介護また障害福祉サービスが受けられるよう、各自治体が、把握したニーズを踏まえまして、地域で必要なサービスの確保に努めているものと承知しております。
厚生労働省といたしましても、引き続き、情報把握を行いながら、石川県や市町と連携をして対応してまいりたいと考えております。
堀川委員 ただ、やはり現地の方々のお話を聞いていると、事業所の職員がなかなか戻ってこられない状況がある中で、広域避難された高齢者の方々なんかが戻りたくても戻れないような状況もいまだにあるというふうなお話を聞いています。
ちょっと時間がないので三番目の質問は飛ばすんですけれども、事業所の職員がどの程度戻ってきているのか、あるいは、帰還を望まれている被災者の方々がどの程度施設や地域に戻ってきているのかというふうなことを厚労省はつかんでいないということでした。是非これは政府として把握をするべきだということは強く求めておきたいというふうに思います。
最後に、大臣の方にお伺いをしていきたいというふうに思うんですけれども、奥能登の、先ほどの六市町の自治体で、昨年の一年間で介護や支援が必要な高齢者数が急増したというふうな報道がありました。その要因について自治体の担当者は、広域避難した人が環境激変により避難先で介護が必要な状態となった、あるいは、避難先の環境変化によって認知症の症状が進行したというふうなことを話されているようです。やはり、広域避難による環境変化が被災者の心身に及ぼす影響ということは、これまでも様々指摘をされています。
高齢者施設や障害者施設からやむを得ず広域避難した被災者が望めば元の地域に戻るということは、生活再建にとって不可欠だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
坂井国務大臣 委員御指摘のような状況が今生まれていることは承知をしておりまして、こうした方々が元いた施設に早期に戻っていただくということは大事でございますので、厚生労働省において、被災した高齢者施設等の早期復旧を図るため、施設復旧支援や復旧手続の迅速化のための特例的な取扱いといった取組、これも、今までも講じられてきましたけれども、また今後、委員が御指摘のような様々なデータの把握などもしながら進めていっていただいて、それぞれの希望に応じて一日も早く元の生活を取り戻すことができるよう、厚生労働省や石川県と連携してまいりたいと思います。
堀川委員 その際に、やはり元いた地域の医療、福祉関係施設の機能の再建というのが大前提となるというふうに思います。この機能の再建というのは、施設の建物だけではなくて、必要な機材や、そしてその施設を運営する職員が戻ってくるということが重要だというふうに思います。それはやはり、広域避難の被災者に限らず、そこで働く人がいるということは、なりわいの再建にもなるし、地域の再生にもつながっていくというふうに思うんですね。
能登の復興を考えたときに、この医療、福祉関係施設の再建の意義と役割というものは本当に大きなものがあるというふうに考えていますけれども、そこについて、最後、大臣のお考えをお聞かせください。
坂井国務大臣 医療や福祉を必要とする皆さんは、そこにそのサービスを提供できる環境がなければ戻りたくても戻れないという環境、状況でございますから、すごく大事なことだと思います。そして、財政的な面もそうですが、人的な面も大変課題になるという御指摘もありました。
これは医療、介護の分野だけではなくて、能登半島全体もそういった困難に直面をしているということかと思いますが、局所というか、この医療、介護の分野だけではなくて、地域の課題としてもしっかり取り組んでいかなければならない課題であろうかと思います。
内閣府としても、被災した、今御指摘いただいたような高齢者施設等の施設の再開は、地域の復興のためには重要であると考えておりますから、引き続き厚生労働省や石川県と連携をし、そしてまた、それと同時に、まちづくり、地域としての復興にも人が来る、戻ってくるということは大事でございますので、こういった意味での復興を図ってまいりたいと思っております。
堀川委員 能登の人々が自分たちの地域を取り戻していく上で、やはり医療、福祉の関係の再建ということは要になってくるというふうに思います。引き続きこの問題は取り上げていきたいというふうに思っていますので、これで質問を終わります。ありがとうございます。