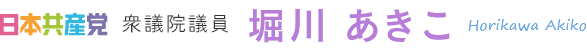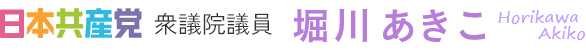国会質問
国会質問


「事業再建資金融資の返済が生活と生業(なりわい)の再建、地域経済の再生の足かせとならないように柔軟な運用を」。日本共産党の堀川あきこ議員は13日の衆院東日本大震災復興・防災・災害対策特別委員会で、被災事業者が置かれた状況を踏まえた柔軟な支援を求めました。
東日本大震災でグループ補助金を利用した岩手、宮城、福島3県の事業者のうち、自己負担分を無利子融資「高度化スキーム貸付」でまかなった事業者が、事業環境の変化などで再建が軌道に乗らず、返済を繰り延べする実態が相次いでいます。堀川氏は、暮らしと事業の再建が道半ばの事業者に対し、画一的な対応ではなく、個々の状況に即した柔軟な対応をと求めました。
赤沢亮正経済再生相は、被災事業者の二重債務問題に対応するとして国と石川県、地域金融機関などが共同出資で昨年4月に設置した「能登半島地震復興支援ファンド」による支援を含め、「被災事業者がおかれた環境を十分に踏まえて、事業者に寄り添った柔軟な対応をしてもらうことが極めて重要である」と答弁しました。
堀川氏は「被災地の地域経済の再生は被災事業者の生業再建なしには進まない」と述べ、能登では展望が持てない状況が続いており、被災事業者に対する支援の活性化が求められると強調しました。
(しんぶん赤旗2025年5月17日付掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。
今回の法改正は、能登半島地震も受けて、被災地の事業者支援の位置づけを高め、被災地の地域経済の再生を目指すものというふうに理解をしています。
被災事業者支援で地域経済の復興を促進する制度として、東日本大震災のグループ補助金があります。被災事業者の運動と世論でつくってきた制度であり、生活となりわいの復興という重要な役割を担う一方で、コロナ禍や物価高騰なども影響し、事業再建がなかなか進んでいないというふうな状況があると思います。
中小企業庁にお聞きをしたいんですけれども、このグループ補助金の四分の一の自己負担分を無利子融資で賄った事業者が返済期間を延長するなど返済が滞っている状況についてどう把握しておられるか、その原因と対策について説明を求めたいと思います。
岡田政府参考人 お答えいたします。委員御指摘のございましたグループ補助金でございますけれども、四分の三の補助率としておりますので、当該補助金の交付決定を受けた事業者が四分の一の自己負担分の資金を調達する場合には、独立行政法人中小企業基盤整備機構と被災各県が連携いたしまして、県の支援機関を通じた長期、無利子の貸付けを行っているところでございます。
中小機構を通じまして、委員も御指摘ございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響など事業環境が変化したことによりまして経営状況が悪化してやむを得ず返済期間を延長している事業者がいることを承知してございます。
このため、中小企業庁といたしましては、令和二年三月に、中小機構に対しまして、資金の返済が困難な事業者から返済猶予の相談があった場合には柔軟に対応するように要請しているところでございます。
さらに、返済期間を延長した事業者に対しましては、返済計画を始めとした様々な経営課題につきまして、中小機構、被災各県及び県の支援機関が連携いたしまして、個別相談あるいは専門家派遣等を通じた支援を実施しているところでございます。
引き続き、中小機構と連携いたしまして、被災事業者に寄り添って丁寧な対応をしてまいりたいと考えております。
堀川委員 ありがとうございます。
このグループ補助金の趣旨は、生活となりわいの再建であり、地域経済の再生にあるというふうに理解をしています。計画どおりになかなか再建が進まない事業者に対してこの返済が逆に足かせとならないように、柔軟な運用を求めたいというふうに思います。
続いて、REVICに関してなんですけれども、活用する事業者は、なりわい補助金も受けることができないような事業者が利用することが多いというふうにお聞きをしました。能登にもファンドがつくられていますけれども、計画どおりに再建が進まないということも今後十分起こり得るというふうに思います。
REVICの融資などの再建支援で当初の計画どおりに再建が進んでいない事例はあるかどうか、その場合どのような対策を取られているのか、内閣府、お願いします。
野崎政府参考人 お答え申し上げます。REVICが取り組む事業再生支援においては、委員御指摘のとおり、仮に当初策定した事業再生計画どおりに再建が進まない場合には、事業者に寄り添い柔軟に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
事例のお話が御質問に出ましたが、例えば、REVICが参画する復興ファンドにおきまして、熊本地震のファンドの事例でございますけれども、地震により被害を受けた事業者、旅館だったんですけれども、そこが立て直しのためにREVICの支援を受けておったところ、その後、コロナ禍に直面しまして更なる追い打ちを受けて資金繰りが厳しくなって、そうした場合に、金利を一時的に引き下げるなどの弾力的な対応を行い、無事にコロナ禍を卒業して旅館を再生に導いたというような事例もございます。
今後も引き続き、REVICにおきましては、事業者にとって最善の再建計画を策定することを支援するとともに、仮に当初の計画どおり再建が進まない場合にあっては、柔軟に対応を行っていくように促してまいりたいというふうに考えております。
堀川委員 ありがとうございます。伴走型の支援ということでREVIC法でもうたってありますので、是非柔軟な支援をお願いをしていきたいと思います。 最後に大臣にお聞きをしたいと思うんですけれども、被災地の地域経済の再生というのは、被災事業者のなりわいの再建なしには進まないというふうに思います。その肝腎要の事業者支援の在り方について、大臣はどのようにお考えか、最後、見解をお聞かせください。
赤澤国務大臣 被災地域の経済の再生にはなりわい支援が非常に重要である、不可欠であるという御指摘は、全くそのとおりで、共有をいたします。
委員御指摘のとおり、REVICが被災事業者に対して出融資等の資金支援を行うのは、今御指摘のあった、本当に重要である事業者のなりわいをしっかりと再建するためであります。
被災事業者の中には、支援期間中、先ほど政府参考人から話しましたコロナ禍が起きたとか、いろいろな経済社会情勢の変化で事業環境が大きく変化してしまう場合もございます。そうした場合にも、その時々において事業者に寄り添って柔軟な対応を行っていくことが極めて重要である点は、まさに今日この質疑で委員が明らかにしてくださったとおりでありまして、REVICにおいても、今後も引き続き、それぞれの被災事業者が置かれた環境を十分に踏まえて、事業者に寄り添った柔軟な対応をしてもらうことが極めて重要であるというふうに考えております。
堀川委員 ありがとうございます。改めて強調しますけれども、やはり、被災地の地域経済の再生というのは、被災事業者のなりわいの再建なしには進まないというふうに思います。能登の状況を見ても、なかなか展望が持てないというふうな状況が続いている中で、この法改正によって被災事業者の支援がより活性化するということを期待しまして、私の質問を終わらせていただきます。