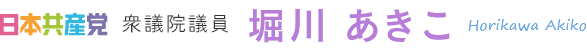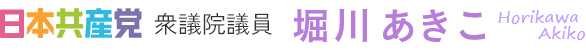国会質問
国会質問


日本共産党の堀川あきこ議員は4日、衆院国土交通委員会で、港湾法改正案の質疑に立ち、港湾施設の老朽化対策に必要な技術職員の増員と予算の拡充を求めました。
改正案は、全国の港湾施設の老朽化・陳腐化が進み、港湾の技術職員が不足する中で、国による工事代行制度などを創設します。
堀川氏は「技術系職員が減り、メンテナンス工事が困難になっている。この間の職員削減など国の政策を根本的に見直すべきだ」と指摘。技術系職員がゼロの港湾管理者(自治体)が22もあるとして、港湾をどのように維持管理しているのかとただしました。
国交省の稲田雅裕港湾局長は「民間コンサルタントの力を借りながら工事にあたる取り組みを推察する」と答弁。堀川氏は「しっかり実態を把握すべきだ。国の港湾職員の体制も限界だ。国の人員増、体制強化に踏み出すべきだ」と迫りました。中野洋昌国交相は「国の港湾関係の技術職員も確かに減少傾向」だと認め、「国の職員の体制強化も必要であり、技術職員の確保と育成に全力で取り組む」と答えました。
国交省の「インフラ長寿命化計画」では2019年度から30年間の維持管理・更新費は国交省全体で180兆~190兆円にのぼり、うち港湾は約6兆~8・3兆円と推計しています。
堀川氏は「国交省が集めた地方自治体の意見や検討会でも予算不足という意見が多かった。今後、港湾だけでなく全体のインフラ老朽化が進んでいく。資材の高騰もあるなかで、将来推計を見直すべきだ。国として老朽化対策のビジョンを示すべきだ」と要求。中野国交相は「次期計画の策定にあわせて見直しを検討したい」と答えました。
(しんぶん赤旗2025年4月10日付掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。早速質問に入らせていただきます。
本法案は、港湾の老朽化、陳腐化が進む中、インフラ機能の確保のために支援が必要という背景から、国による工事代行制度の創設などが新たに盛り込まれています。
この港湾の老朽化対策についてなんですが、老朽化していくということは予測できたことだというふうに思うんです。この間、国交省として取り組んできた老朽化対策について、先ほどの井上委員の答弁と重なる部分があるかもしれませんけれども、この間の対策と実績について答弁をお願いします。
稲田政府参考人 港湾施設の老朽化対策につきましては、将来にわたってその機能を発揮できるよう予防保全型の維持管理への本格転換を図るため、老朽化した施設の機能集約を行う再編や、新技術の活用などに取り組んできてございます。
令和四年度には、これまで交付金で行っていた老朽化対策のための事業を集中的に支援する個別補助化を行いました。また、ライフサイクルコストの縮減や、機能の集約及び転換、DXを含む新技術等の活用などを港湾施設の維持管理計画に盛り込むための補助制度も創設をいたしました。
さらに、港湾施設の老朽化に関する情報を電子化して、一元的なアクセスを可能とするサイバーポートの構築や、新技術の活用による点検の合理化などの取組も推進してきてございます。
堀川委員 今述べられたことなんですけれども、これはインフラ長寿命化計画に基づいてやってきたことという認識でよろしいですよね。確認です。
稲田政府参考人 そのように捉えていただいて構わないと思います。
堀川委員 ありがとうございます。この法案でも強調されているように、ただ、老朽化は今後急速に進む、しかし、そのための工事が困難になっているという事態が指摘をされています。
この間の老朽化対策、今述べられたことなんですけれども、国交省としてどう評価しているのか、十分だという認識なのか、認識を問いたいと思います。
中野国務大臣 先ほど港湾局長から、港湾の老朽化対策の取組ということで、今やっていることを紹介をさせていただきました。国土交通省では、老朽化対策に係る様々な取組を推進をしてきたということでございます。
他方で、やはり港湾施設の整備というのは、高度経済成長期に集中的に整備をしたものが多うございますから、老朽化は急速に進行しているというのが現状でもございます。老朽化対策の推進というのは、引き続き、喫緊の課題である、そういう認識をしております。
そういう意味では、引き続き、例えば予防保全型のメンテナンスへの転換、あるいは、先ほども少し御紹介させていただきましたDXを含む新技術の活用などもしっかり活用して、更に戦略的そして計画的に老朽化対策を推進をしていきたい、このように考えております。
堀川委員 あまり、ちょっと評価という中身がなかったような答弁だと思うんですけれども、やはりこれだけ技術系職員が減ってきている、そのことによってメンテナンスの工事が困難になってきている。やはり、この間の職員の削減あるいは地方交付税の削減など、根本的な国の政策を見直すべきだと私は思います。そのことは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
今、先ほど、港湾の技術系職員が不足している、そしてゼロの自治体もあるということで、その自治体数が二十二の自治体というふうに井上委員の質問の中でも答弁がありました。そうした港湾技術の職員がゼロの自治体、これは今どうやって港湾の維持管理をされているのでしょうか。
稲田政府参考人 つぶさに情報を得ているわけではございませんが、事務系の方しかいないという中で、多分、民間コンサルタントの方等の力をかりながら、発注図書を作成し、工事に当たるというような取組をされているものと推察してございます。
堀川委員 多分ということではなくて、しっかり実態を把握するべきだというふうに思います。
次の質問なんですけれども、今回、そういった事態もある中で、国による工事代行の制度が創設をされているということですが、あくまで応急措置だというふうに思うんですね。一方で、国の港湾職員の体制も限界がある。この間、人員体制が確保できないと、工事代行というふうに言われてもなかなかそれに対応できない、こうした声も聞こえてきています。
港湾の維持管理というのはやはり高度な技術が必要だ、人材の確保、育成というのはやはり大きな課題だというふうに思います。国の体制も限界があるという職員の声がある中で、やはりこういう声に対して、国の港湾関係の人員増、体制強化に踏み出すべきだというふうに思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
中野国務大臣 お答え申し上げます。地方自治体においては、先ほど局長からも答弁ございましたが、全国百六十六の港湾管理者のうち、全体の約六割に当たる百一の港湾管理者では技術職員は五名以下で、先ほどありました全体の一割に当たる二十二管理者では技術職員は不在という状況でございます。
一方で、委員御指摘のとおり、国の港湾関係の技術職員も確かに減少傾向にはございます。他方で、一定規模の職員数を国は有しているものでございますから、今般の代行制度を創設をするものでありますが、港湾施設の老朽化が進行し、計画的、戦略的な老朽化対策が必要となる施設が急増する中で、国の職員の体制強化も引き続き必要であるというふうに認識をしております。
国土交通省としては、採用活動の強化による技術職員の確保や、港湾管理者の職員等も対象とした港湾施設の設計、施工に関する研修により、港湾に関する専門知識を有する技術職員の育成を行うなどの取組を行っているところであります。
国土交通省として、引き続き、港湾関係技術職員の確保と育成に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
堀川委員 体制強化は喫緊の課題だというふうに思いますので、是非取り組んでいただきたいということを重ねて求めたいというふうに思います。 続いての質問なんですけれども、もう一つ、この老朽化対策に関する予算措置についてです。
最初の質問で、インフラ長寿命化計画(行動計画)について触れたんですけれども、この計画では、維持管理・更新費の将来推計を国交省が出しておられました。港湾の場合なんですけれども、港湾は二〇一九年度から二〇四八年度までの三十年間の維持管理・更新費、これは幾らと推計しておられたでしょうか。
稲田政府参考人 平成三十一年にこれを出させていただいていますが、三十年間の維持管理・更新費の推計、全体百八十から百九十兆円のうち、港湾は約六から八・三兆円というふうな数字が出ていると思います。
堀川委員 この計画の中には、五年後、十年後、二十年後、そして三十年後、その維持管理・更新費というのも刻んで出されているんですね。五年後、つまり二〇二三年度になるんですけれども、二〇二三年度は三千億円というふうな記載がありました。これは、実績はどうなっているか分かりますか。
稲田政府参考人 先ほど申し上げた数字は、港湾管理者さんの地方単独費だとか、いろいろな数字が混ざった数字として公表されております。
一方で、我々の方の予算、直轄事業や補助事業、そういった中で、維持管理にそれがどのくらいかかったか、更新にどれくらいかかったかというのを、そこだけ取り出して数値化するというのが難しいことがありまして、現時点ではどの程度必要になったのかを把握はできておりませんし、することも困難かというふうに思っております。
堀川委員 国交省が取った港湾管理者の意見の中、地方自治体の様々な意見の中に、この港湾工事の維持管理、予算不足という意見が多数あったというふうに聞いております。
先ほど、技術系職員が一人もいない自治体の港湾の維持管理についてお聞きをしましたけれども、こういう自治体、先ほど答弁があったように、民間のコンサルだったりとか外部業者に委託をするということがあると。ただ、その委託料も負担になっているというふうな意見も中にはあったかというふうに思います。国交省が設置した検討会の中でも、この予算不足というのが指摘をされています。
昨今の物価高もあって、資材高騰もあって、二〇一八年度に立てた将来推計というのが今なかなかちょっと通用しないものになってきているというふうに思うんですけれども、今後、インフラの老朽化、港湾だけでなく全体が進んでいくというふうな見通しを国交省は持たれている中で、この将来推計というものを見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
中野国務大臣 国土交通省のインフラ長寿命化計画においての推計、先ほど来議論をしてまいりました。この推計につきましては、DXなど新技術やデータの積極的活用等、効率化が図られる、そういう減らしていくという要因もあるとともに、当然、御指摘のような資材価格が高騰する、労務費が上昇する、上昇をするような要因もあるところだと思っております。
国土交通省インフラ長寿命化計画の計画期間というのは令和七年度までとなっておりますので、維持管理・更新費の推計につきましても、次期計画の策定に合わせて見直しを検討してまいりたい、このように考えております。
堀川委員 インフラの老朽化対策ということで、この国土交通委員会でも今後も議論になっていくと思うんですけれども、国交省としてこれに対してどういう対策を行っていくのかというビジョンを是非示していただきたいですし、示すべきだというふうに思います。
最後の質問なんですけれども、今回の法案の中で、非常災害時の場合における土地の一時使用等で、他人の土石等を活用できるというふうになっています。新設するその条項の第二項の中で、災害で被害を受けた荷さばき地の応急復旧のために、他人の土地を一時的に使用、収用できるようにするというものです。
他人の土地、建物、つまりこれは私有財産ということになるわけなんですけれども、所有者の了解なしに使用することを認めるという異例の措置だというふうに思うんです。
憲法二十九条は、「財産権は、これを侵してはならない。」というふうに規定をしています。国交省の説明によりますと、その三項で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」というふうな規定から、非常災害時の利用は公共のための利用として説明をされています。しかし、災害時とはいえ、これは憲法上の疑義を感じる国民がいるというのは当然のことだというふうに思うんですね。
この非常災害時の利用ということは極めて慎重な判断が必要だというふうに思いますが、その点についてお伺いしたいのと、また、日頃から地権者、その関係者への説明など、周知徹底する必要があると思いますが、いかがでしょうか。
中野国務大臣 御指摘の応急公用負担規定につきましては、御指摘のとおり、一定の財産権の制限につながるものでございますので、その発動条件は、緊急物資輸送のために港湾施設の応急復旧を緊急に行う必要があり、ほかに手段がないと認める場合に限定をさせていただいております。その上で、既存の応急公用負担の制度と同様に、損失が生じた場合の補償の規定も設けることとしております。
本制度の施行に当たりましては、港湾管理者向けの説明会や通知等の発出により、損失を受ける可能性のある関係者との平時からの関係構築や、本制度について関係者の理解を得ておくことの重要性を周知をすることで、適切な制度の運用を図ってまいりたい、このように考えております。
堀川委員 質問を終わります。ありがとうございました。