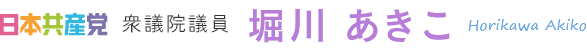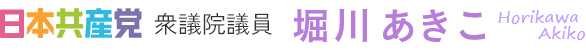国会質問
国会質問


日本共産党の堀川あきこ議員は21日の衆院国土交通委員会で、大阪・関西万博開催に伴う関西空域での新飛行経路の運用開始によって、騒音被害や航空管制官の業務負荷増などの問題が生じているとして、新経路の見直しを求めました。
新経路の運用は、関西経済連合会などが参加する「関西3空港懇談会」の要請を受け関西万博開催に間に合わせ3月20日に開始。関西国際空港では1時間当たりの最大発着回数を46回から60回に、神戸空港では国内線で1日最大80回から120回に拡大し、国際線も解禁しました。このため、淡路島上空の飛行が増え、従来の飛行制限高度よりも低い高度による飛行も可能になりました。
堀川氏は、新経路運用開始から淡路島上空を通過した航空機が1カ月で延べ9538機(1日平均318機)にのぼり、一部地域では騒音がひどくなったとの苦情があると指摘。また、関空の出発機の大半が標準経路からそれて特定のルートに集中しているのは、1機ごとに針路を指示するレーダー誘導をせざるを得なくなっていることに伴うもので、このため管制官の業務量が増えているとして、管制体制の実態をただしました。国交省の平岡成哲航空局長は関空の管制官に12人もの欠員が生じていると明らかにしました。
中野洋昌国交相は「レーダー誘導の実施が直ちに管制官の業務量増加に結びつくものではない」などと管制官の業務負荷の実態を軽視する姿勢を示しました。
堀川氏は「関西財界の要求、万博・カジノありきで空の安全対策が二の次にされている」として、新経路の見直しを求めました。
(しんぶん赤旗2025年5月23日付掲載)より抜粋
資料
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。本法案は、羽田空港での航空機衝突事故も受けての提案というふうになっています。様々な再発防止策が議論されているんですけれども、大きな背景として航空便の過密化があるというふうに考えています。この羽田と同じような事故を、ほかの空域でも起こしてはならないというふうに考えます。
関西空域で今年三月二十日から始まった新経路、運用見直しについて質問をしていきたいと思います。
関西空域では、関西経済連合会、知事、政令市の首長などが参加する関西三空港懇談会の要請を受ける形で、飛行ルートや発着回数の増加が決定をし、今年、二〇二五年三月二十日から実施をされています。この懇談会では、大阪・関西万博、IR、カジノですね、関西圏の経済発展のためというふうな議論がされております。
三月二十日からのこの見直しについて、万博の開催に間に合わせたというふうな理解でよろしいでしょうか。大臣、イエスかノーでお答えください。
中野国務大臣 関西空港の新飛行経路は、二〇二五年の大阪・関西万博の成功を支えるとともに、増加する訪日外国人需要への対応など、その後の関西の持続的な成長を支えることなどを目的として、本年三月二十日から導入をされたものでございます。
堀川委員 関西空域は、関西国際空港、神戸空港、伊丹空港、さらに自衛隊と共用の八尾空港が近距離にあり、元々狭い範囲に複数の空港が密集しているというふうな空域になっています。
今回の運用見直しの主な内容なんですけれども、関西国際空港が一時間当たりの最大発着回数を四十六回から六十回に増やしていくと。神戸空港は一日の最大発着回数を国内線で八十回から百二十回に増やし、国際線はこれまでなかったんですけれども、一日四十回まで解禁をされました。このため、淡路島上空を横切るコースというのが二ルートから七ルートに増えて、飛行機の高度がこれまでよりも低空が可能となるように緩和をされています。
資料一が関西国際空港の経路見直し案、これは南風のときの出発経路図なんですけれども、淡路島上空を横切るコースが三つ、東浦ルート、南あわじルート、南淡ルートとなっています。北風のときの出発経路もこれは同じコースというふうになっているわけです。これは、済みません、二つ目の質問を飛ばします。この見直し案が三月二十日から正式に採用されているということになっています。
それで、この三月二十日以降、実際にどれだけの機数が淡路島上空を通過しているかというのを資料二に示してあります。見直し後の四月の一か月で淡路島上空を通過した出発機と到着機の運航実績数をまとめたものです。
一か月の機数は、関空の合計が八千百九十八機、神戸空港の千三百四十機を含めると、一か月で九千五百三十八機が淡路島上空を通過しているということになります。これは単純に三十日で割りますと、一日平均三百十八機が通過をしているというふうなことになります。
これは元々、関西国際空港の建設を決定した際に、国の航空審議会の答申に明記をされた、沿岸部の住居地域への騒音影響を考慮して、努めて海上を飛行し、低高度で陸上上空を飛行しないという地元自治体との約束があったわけですよね。基本的にそれが守られてきました。しかし、今回、努めて海上を飛行するという約束が、実態とはかけ離れたものになっているというふうなことだと思います。
淡路島北部の岩屋地域、また南部の由良地域というところからは、淡路島上空の飛行が可能になり、かつ、飛行する高度が低くなったことによって、騒音がひどくなったというふうな声が届いています。
航空局からは、この飛行経路の見直しについて地元合意を取ったんだというふうにお聞きをしたんですけれども、実際、淡路島の住民の方は騒音被害を訴えられているということです。 これは大臣にお聞きしたいんですけれども、この住民の方の騒音被害の声、認識されていますでしょうか。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。関西空域の新飛行経路につきましては、導入前の昨年一月、淡路島市長会から、住民の皆様のお声として、淡路島の陸域の上空に五本の飛行経路が新設をされること、従来の飛行経路と比べて高度が引き下がることから、生活環境への影響や不安の声があるとの御意見があり、運用開始後も地方自治体等に対して住民の皆様からの問合せなどがあったというふうに私も承知をしております。
こうした御意見への対応として、新飛行経路の運用後の住民の生活環境への負担をできる限り軽減をするという観点から、地元自治体、関西エアポート、国などが参画をする府県ごとの関係者会議の設置など、新たな環境の監視体制が整えられたところでございます。
この府県ごとの関係者会議におきまして、継続的に新飛行経路の運用状況の把握や課題等の協議が行われることとなっておりまして、国土交通省としても、地元自治体等の関係者としっかりと意思疎通を図り、安全性の確保を前提として適切に対応してまいりたいと考えております。
堀川委員 その際に、是非、当事者の地元住民の声がきちんと反映されるような運営をお願いをしたいというふうに思います。
それで、三月二十日以降の新たな運用で、空の安全を脅かす事態も起きているようです。関西空域での航空機同士の異常接近、衝突防止装置が作動した事例が一件あったというふうに事前の調査でお聞きしたんですけれども、これは事実でしょうか。確認です。
平岡政府参考人 お答えを申します。関西経路の見直しを行った本年三月二十日から五月十四日までの間でございますけれども、関西空域において、航空法第七十六条の二に基づく、航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認められる事態の機長からの報告はございません。
一方、同期間、同空港において航空機衝突防止装置の回避指示が作動したとして報告のあった事案は一件ございましたが、パイロット及び航空管制官による適切な対応が取られた結果、安全上の問題はなかったと認識しております。
済みません。ちょっと先ほど、同期間、同空港と申し上げましたけれども、同期間、同空域の間違いでございます。大変申し訳ございません。
堀川委員 一件あったというふうなことだと思います。
衝突回避装置の作動というのは、衝突を回避する最後のとりでというふうに言われています。新たな運用が始まって一か月余りの間にこのことが発生したということは深刻だというふうに思うんですけれども、大臣の受け止めはいかがでしょうか。端的にお願いします。
中野国務大臣 先ほど局長から答弁をさせたところでございます。そのような事実があったということは承知をしております。
その上で、本件につきましては、先ほどの答弁のとおり、パイロット及び航空管制官による適切な対応が取られた結果、安全上の問題はなかったと認識をしておりますが、今後、必要に応じ、再発防止に向けた取組を進めてまいりたいというふうに思います。
堀川委員 まだまだ問題が起きているというふうなことを申し上げたいと思います。
資料三は、関西エアポートが公開をしている航跡の重ね合わせ図です。四月二十日の一時台の一時間の飛行航跡を示しています。青が出発機、赤が到着機、かなり多くの割合で出発機と到着機が大阪湾上空、関空と淡路島の間のエリアで交差しているのが分かるかと思います。
資料一にあるように、飛行ルートを増やしたことで、関空からの出発機は淡路島上空を横切る三つのコースが標準経路となりました。しかし、実際の運用では、資料三のように、青線で示した関空からの出発機のほとんどが東浦ルート付近に集中しているということが分かると思います。
資料四は、この四月二十日の航跡図を時間単位でお示しをしたものです。ほとんどの航跡が同じ傾向になっている。ちなみにこの日は曇りだったんですけれども、雨は降らなかったようです。
なぜこうなるのかということで現職の管制官にお話を聞きますと、出発機は離陸後に一定の高度、平均でおよそ一万六千フィートから一万八千フィートまで到達させた上で、神戸や東京の管制部に業務移管することになる。出発機が南あわじルートや南淡ルートの標準経路のとおりに飛ぶと、赤線の到着機がやってくるコースに向かっていくということになるわけです。発着枠の拡大によって、到着機はおよそ二分間隔でやってくる、その合間を縫って出発機の高度を上げるというのは、針の穴に糸を通すようなものだというふうにおっしゃっていました。
一方で、出発機も二分間隔で続いていきます。そうなると、出発機が滞留してしまい、管制官の能力を超える手持ちの機数になってしまう。飛行機が壁をつくっているという表現が管制官の間では使われるそうです。これは、少しでも早く到着機と交差を終えて出発機の高度を上げるために、管制官が南あわじルートや南淡ルートを避けて東浦ルートに誘導をし、結果、東浦コースに集中しているというふうなことがうかがえると思います。
東浦コースに集中していることについて、局長、どのように認識をされていますでしょうか。これも、済みません、端的にお願いします。
平岡政府参考人 お答えをいたします。御指摘の関西空港の出発機が東浦ルート付近を多く飛行していることにつきましては、安全性の確保を前提といたしまして、御地元からの要望である陸地上空の飛行高度の引上げを図るため、管制運用上の工夫により、管制官が誘導した結果であるというふうに認識しております。
堀川委員 今おっしゃいましたけれども、標準経路を避けて東浦コースに誘導する場合、管制官が指示を出してレーダー誘導をしているということだと思います。
見直し前の運用では、関空の出発機というのは、標準経路の飛行で七海里くらいまで直進をして、その間、レーダー誘導は必要なくて、管制官は監視するというのが主な任務だったということです。新たな運用で、管制官は判断も増えるし、見る範囲も広がるし、通信量も増える、明らかに業務量が増えていると思うんですけれども、局長、いかがでしょうか。
平岡政府参考人 お答えをいたします。管制官は、進路、高度、速度を指示することで航空機の安全な間隔を確保しており、進路を指定する手法としてレーダー誘導は標準的に行っていることでございます。そのため、レーダー誘導の実施が直ちに管制官の業務量の増加に結びつくとは考えておりません。
これまでも、航空需要の増大に伴いまして、管制官一人当たりの業務負担が過大とならないよう、適切な体制を確保すべく、増員を行ってきたところです。
引き続き、航空需要の動向や管制官の業務負担の状況等を踏まえ、管制官の人的体制の強化、拡充を含め、航空の安全、安心の確保に向けた取組を進めてまいります。
堀川委員 国土交通労組からは、見直し前の計画の段階で、レーダー誘導ありきの経路は無理があると声が上がっていたと、これは航空局も把握しているはずです。真摯に受け止めていただきたいと思います。
さらに、管制官の人員体制についてもお聞きしたいんですけれども、関西空港事務所の予算定員、実際に配置されている実員数、欠員数、どうなっているでしょうか。数だけお願いします。
平岡政府参考人 令和七年四月一日現在ということでお答えさせていただきます。関西空港事務所航空管制官の定員は百五十五名でございます。
実員につきましては、育児休業や中途退職などにより日々刻々と変化しますが、先ほど申しました四月一日時点で取りますと百四十三名ということでございまして、欠員については十二名ということでございます。
堀川委員 明らかに足りていないというふうなことだと思います。
最後に大臣にお聞きしたいんですけれども、三月二十日以降の飛行経路について、矛盾がいろいろ明らかになっていると思います。見直すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。現在の飛行状況は、先ほど局長が答弁をしたとおり、安全性の確保を前提に、御地元からの要望であります陸地上空の飛行高度の引上げを図るため、管制運用上の工夫により、管制官が誘導をした結果であります。このレーダー誘導の実施が直ちに管制官の業務量の増加に結びつくものではないというのは、先ほども答弁させていただきました。
引き続き、航空需要の動向や管制官の業務負担の状況等を踏まえまして、管制官の人的体制の強化、拡充等に取り組んでいくこととしております。
こうしたことから、国土交通省としては、新飛行経路を再検討する必要があるというふうには考えていないということでございます。
堀川委員 関西財界の要求、万博、カジノが先にありきで、空の安全対策というのが二の次にされているというふうに指摘をしたいと思います。羽田の重大事故の教訓が生かされていません。そういった姿勢を改めるべきだというふうなことを指摘させていただいて、質問を終わります。