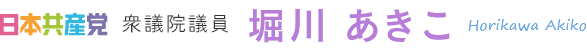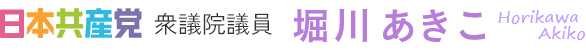国会質問
国会質問


衆院国土交通委員会は9日、マンション関連法改定案に対する参考人質疑を行いました。日本共産党の堀川あきこ議員は、分譲マンションの共用部分に欠陥があった場合の損害賠償請求権について、法案の規定では十分な賠償金が得られず、マンションの完全な補修ができないのではと参考人に意見を求めました。
欠陥住宅被害全国連絡協議会の神崎哲参考人は、法案は分譲マンションの転売後も元の所有者が損害賠償請求権を持ち続けるとの解釈に立っていると指摘。さらに、元の所有者から請求があれば賠償金の返還に応じなければならず、今住んでいる居住者による「完全な補修を阻害する」と批判しました。
また、政府が賠償金の使い道をマンション補修に限定する規約を定めることで対処するとしているが、「現実の紛争や管理規約の実態を全く無視したものだ」と述べ、転売されれば損害賠償請求権も新しい所有者に移転するよう改正すべきだと主張しました。
堀川氏は、法案は損害賠償請求訴訟を起こす際、元の所有者に通知する規定を定めていると指摘。神崎氏は、マンションの転売は9年間で約20%にのぼるとして、「元の所有者を見つけ出すのは不可能を強いるものだ」と批判しました。堀川氏は、管理組合に絶大な負担が生じるとして、マンションの補修が十分にできず、「今住んでいる方の住まいの権利を侵害しかねない」と批判しました。
(しんぶん赤旗2025年5月22日付掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。今日は、参考人の四人の皆さん、お忙しい中、国会の方に出向いていただいてありがとうございます。
私からも損害賠償請求権の問題についてお聞きをしたいんですけれども、その前に、マンション管理、今回のマンション法改正案の今後のマンション管理の在り方そのものについて、齊藤先生の方に御意見をお聞きをしたいと思います。
一つが、タワーマンションの管理の課題についてです。
先日、この法案質疑の中で、タワマンの問題について法案質疑を行ったんですけれども、今後、今、タワマンが都市部を中心に乱立をしているわけなんですけれども、これが老朽化して管理不全になろうものなら、周囲に与える影響というのは本当に甚大だというふうに思うんですね。ただ、先日の質疑で、タワーマンションが抱える課題というのは他のマンションと大して変わらないというふうな答弁があったんです。
ただ、投機目的の購入であったり、先ほど来からもありますように、外国籍の方の購入なども増えているというふうな中で、マンション内の合意形成が困難なように見受けられます。
このタワーマンションについて、齊藤先生、以前にもこの管理の課題について幾つか御指摘をされていると思うんですけれども、そのお考えと、どのような管理の在り方が望ましいのかということでお聞かせいただければと思います。
齊藤参考人 御質問どうもありがとうございます。
タワーマンションというのは、おっしゃるように、都市に与える影響が大きいために、やはり、タワーマンションというものをどういうふうに造っていくのかというのは、都市計画やまちづくりとの、そのプランの中でしっかり位置づけていく必要があると思います。
そして、タワーマンションというのも、私もここには問題が多いんじゃないかと思っていろいろ研究させていただきましたが、結論として申し上げますと、タワーマンションだからこんな問題が起こるというよりか、いろいろな要因が入ってくる。例えば、規模が大きい。そうすると、一般的にマンションで規模が大きいと、どうしても参加への関心が低くなっていく、あるいは合意形成が難しい。そして、さっきおっしゃられましたように、高さが高いことによって、持たなければいけない建築の様々な施設があるというようなことから、専門性が求められていくということがあります。
そして、何か、修繕費が足りないね、じゃ、値上げをしようというふうになってもなかなか合意形成ができないということがありますので、やはり一つは、他のマンションと同じように、基本的には、管理の初期設定をちゃんとして、そして修繕積立金が足りないということがないようにというようなこと。
それから、管理が適正に行っていけるようにという意味では、先ほどから御案内しているような、管理計画認定制度をしっかり取って、それを目指してみんなで共通の目標にしていきましょうよ。例えば、資産価値にすごく敏感な人たちは、そういったことを取ることによって資産価値が上がるということに合意をしていただきやすくなると思いますので、そういう意味では、目標像をしっかり共有して、みんなでしっかり管理をしていくということをサポートしていく必要があるのではないかと考えているところでございます。
堀川委員 ありがとうございます。それでは、もう少し、時間があれば最後にまたお聞きをしたいと思うんですけれども、先ほど来から論点になっています損害賠償請求権についてお聞きをしていきたいと思います。神崎弁護士にお聞きをしていきたいと思います。
二十六条の損害賠償請求権について、改正案では、管理者が旧区分所有者を代理することを認めた上で、ただ、別段の意思表示をした場合はその限りではないというふうなことで、その問題点について、ちょっと改めて見解をお聞きできたらというふうに思います。
神崎参考人 御質問ありがとうございます。
まず、理論的な問題として、おっしゃっている御指摘の点につきましては、理論的に二個問題があると思っております。
まず、別段の意思表示以前に、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権が共用部分の共有持分権と同様の性質を持つのに、そもそも区分所有関係から離脱した旧区分所有者に帰属を認めること自体が、区分所有法十五条一項の随伴性や十五条二項の分離処分の禁止に反するという前提で、分属しているということ自体が間違っているんじゃないかという、その一点目。
そして、その行使方法において、別段の意思表示というのは、管理者が一元行使すべきものを、別段の意思表示によって個別行使を認める法律になりますので、自己の持分の請求権を別途に個別行使することを認めるのは、共用部分の分割請求を認めるに等しいので、区分所有法の大原則に反する。
そういう意味では、理論的には、その二つの大きな問題があります。
そして、実態的に見た場合には、これは完全な補修を阻害するという問題があります。このような分属を認めて、別段の意思表示を認めると、共用部分の欠陥の一〇〇%補修が実現できなくなるわけですね。
例えば、訴訟手続上で考えてみると、紛争解決を阻害するわけです。実際の欠陥マンションの訴訟プロセスで考えても、極めて不都合な事態を招きます。別段の意思表示は訴訟提起後でも可能とされているので、恐らくなら、和解を阻害するであろうと考えられます。
訴訟上の和解協議は、瑕疵修補による和解提案が業者側からなされることもあって、マンションのような大規模建物の場合、修補による和解の方が現実的なケースもあり得るんですけれども、旧区分所有者は瑕疵補修では何ら得るところがないために、業者が瑕疵を認めて瑕疵修補を申し出た途端に別段の意思表示をして、金銭賠償を要求する可能性が高い。瑕疵を認めているんだったら、修補せずに私にお金をよこしなさいよと、別段の意思表示をそのタイミングでしてくるということになろうかと思うんですね。せっかくの補修和解が頓挫する結果を招く。
あるいは、管理組合は、和解するために、具体的な和解内容を議案として管理組合総会に諮り、決議を経る必要があるんですけれども、和解協議の最中に旧区分所有者から一人でも別段の意思表示がされれば、そのたびごとに総会決議を取り直さなければいけないということになって、和解の機会を奪うでしょう。
そして、訴訟提起後に別段の意思表示がなされるのは、このような解決が近づいたときである可能性が高く、旧区分所有者が自ら訴訟追行するリスクやコストを取らずに、漁夫の利を得ようとして紛争解決を阻害すると思われます。
このように、団体訴訟である欠陥マンション訴訟において個別行使を可能とするような仕組みを組み込むこと自体が間違っていると思います。
また、今申し上げたのは訴訟のプロセスですけれども、訴訟が終わった後、現に賠償金が得られた後に、よこせと言うことができるわけですね。別段の意思表示もしないまま、そのまま訴訟を終わって、賠償金が得られることになったときに、自分の持分をよこせと言えるということは、非常に不都合が生じますよね。補修ができなくなっちゃいます。
もし和解の補修工事が完了していたら、現区分所有者全員に対して、旧区分所有者から不当利得返還請求ができてしまうということも考えられるわけです。そうした場合に、例えば修繕積立金を差し押さえて、自分の分をよこせと言われてしまうと、せっかく補修できているのに、今後の改善計画が成り立たなくなってしまいます。
このようなことを許すということが、そもそもたてつけとしておかしいんじゃないかと思っております。以上です。
堀川委員 詳しい御説明をありがとうございます。
この改正案の二十六条の五のところ、旧区分所有者への通知についても定めてあります。この管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は遅滞なく旧区分所有者にその旨を通知しなければならないというふうな規定になっているわけなんですけれども、管理者の立場の方々から、この点について様々な懸念、実際お聞きもしました。
この旧区分所有者への通知に関して、神崎先生の御意見をお聞かせください。
神崎参考人 御質問ありがとうございます。これは、極めて重大な問題もそこにもあります。
戸数の多いマンションで転売が多数生じている場合、多数の旧区分所有者に通知をすることは非常に困難であり、場合によっては事実上不可能となります。
私の配らせていただいている資料三、九十四分の十を御覧いただきたいんですけれども、これは国交省の資料で、マンションの流通量を示しているわけですけれども、二〇一五年以降の九年間で見ても、既存マンションは毎年十三・五万戸から十六万戸、この九年間の間に百三十二万戸が譲渡されています。仮にマンション戸数が七百万戸と仮定して、単純計算しても一八・九%、実に二〇%近くが転売されていることになるわけですね。
そうすると、そのような多数の旧区分所有者を調べて、どこに住んでいるかを調べて通知をするということは極めて非現実的で、不可能を強いるものじゃなかろうか。しかも、それが旧区分所有者による請求行為を招いてしまう。旧区分所有者が別段の意思表示をするきっかけになるだろうし、あるいは、別段の意思表示をしなくても、賠償金が得られた後に分割要求をする契機になる。このようなものを管理者に課すというのは、非常に不都合だなというふうに考えております。以上です。
堀川委員 ありがとうございます。
本当に物すごい実務量になってしまうということと、なかなか難しい作業になっていくというふうなお話なんですけれども、その中で、旧区分所有者の住所を調査をするという方法もあれば、それで大変苦労されたというお話が先ほどもありましたけれども、あとは公示による通知についても今回認められるということになるんですけれども、こうした措置ではやはり不十分というふうなお考えでしょうか。
神崎参考人 御質問ありがとうございます。
確かに、この場合の通知は、意思表示に準じて、民法九十八条の準用により公示送達申請手続を取り得る可能性があります。債権譲渡の通知なんかと同じような形ですね。しかし、公示送達申請手続には手間とコストがかかります。まず、要件が非常に厳格でして、いわばフィクションで届いたことにするわけですので、住んでいないことがはっきりしなきゃいけないわけですね。
そのためには住所をきちんと調べなきゃいけないということで、現地に赴き、例えば具体的に言うと、住所地とされるところに、現地に赴いて、近隣に聞いて、あそこに住んではりませんかねということを聞いて回ったりとか、郵便受けを調べたりとか、電気メーターとかが回っていないかを調べて、夜、電気がついていないか見に行けとか、昼間は分からぬから、夜、見に行けとか、洗濯物が干されていないかとか、そういうことを見に行けというようなことを裁判所から言われたりするわけです。
ポストの中なんか、どうやって見るんですかという話なんですけれども、裁判所は平気で言うので、プライバシーの侵害じゃないかと私なんかは思うんですけれども、そういうことをやった挙げ句に、それが遠方だった場合、一体どうするんですかという話になるわけですね。それが一件だけでも大変なんです。
我々は、訴訟をやるときに、公示送達という手続になったときに、そういうふうな手続を取らなきゃいけないことが間々あって、泣きながらやるわけですけれども、これがマンションになって、先ほど申し上げたように、私がやった事件でしたら、六百五十四戸の中で百五十戸も移転している。百五十戸、全部届かないということはないと思うんですけれども、そのうち例えば二、三割でも分からなくなっていれば、もうそれだけでも膨大なコストになるわけで、しかも、転々流通していくわけですよね。そうすると、前の人を遡って、その前の前に遡っていくというようなことになって、すごく大変なことになる。これはもう極めて非現実的なことではなかろうかと思います。
当然承継にすると、そんなことをする必要は全くないわけですよね。通知すらする必要がなくて、登記で今の現在の区分所有者を調べればいいので、法務局に行って登記を上げる、それだけで済むわけです。どちら側が現実的なのか、もうすぐに分かりますよね。なので、当然承継説が優れていると考えます。
以上です。
堀川委員 もう時間が来そうなんですけれども、先ほど来からお伺いをして、まず管理者の方への絶大な負担ということが今でさえ存在しているというふうな中で、更なる負担が生じる可能性もあるというふうな御指摘だったというふうに思います。探偵のようなやり方で、そこまでやらせるのかというふうなことは、ちょっと正さなければならないなというふうに改めて思いました。
今回、この旧区分所有者に関する区分所有権の問題で、沖野先生、中野先生、神崎先生それぞれのお考えを聞かせていただいたんですけれども、やはり、私は、現実に即して法というのはあるべきだというふうに考えているんですね。今の在り方で、神崎先生が先ほど来から御指摘をされているようなトラブルがもしあれば、今住んでいる方の、区分所有者の方の住まいの権利を侵害するということにつながりかねないということは重大な問題だというふうに改めて認識をさせていただきました。
時間が来ましたので終わりますけれども、引き続き、皆さんにいろいろ御意見をお伺いしながら、このマンション管理の在り方について今後も深めてまいりたいと思います。今日はありがとうございました。