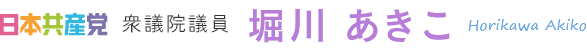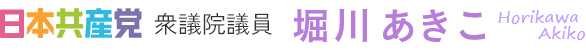国会質問
国会質問


老朽化マンションの建て替え「円滑化」などを目的としたマンション関連法改定案が15日の衆院本会議で、自民、公明、立憲民主、日本維新の会、国民民主の各党の賛成多数で可決されました。日本共産党とれいわ新選組、有志の会は反対。改定案は立民提出の修正案を反映しています。
日本共産党の堀川あきこ議員は14日の国土交通委員会での討論で、マンションの老朽化が深刻になるもと、政府の対策は居住者の居住の安定を担保する施策が不十分で「根本的な解決を図るものになっていない」と批判しました。
建て替え決議要件の緩和はやむを得ないが、建て替えに参加しない反対少数者への保護がほとんど講じられず「反対少数者を置き去りにしたまま建て替えだけが進められる危険をはらんでいる」と述べました。
今回の改定で、分譲マンションの共用部分に欠陥があった場合、訴訟で得られた賠償金は、売却・退去していても最初の購入者に権利があるとされます。賠償金をすべて補修に充てられず「今住んでいる人の生活の安定を侵害しかねない」と指摘しました。
さらに、建て替え決議が議決されれば賃借人の追い出しを可能にする、新たな賃借権の終了請求制度を盛り込んでおり「今でも横行している賃借人への強引な立ち退きを増長させる」と批判しました。
質疑で堀川氏は、居住者の追い出しの実態や、高齢者の住まいの確保が困難になっている実例を紹介。賃貸物件の立ち退きは現在でも正当事由のない明け渡しが圧倒的で、わずかな立ち退き料で泣き寝入りしており、高齢者が入居を何度も断られ、住まいが見つからない実例を示し「居住者の老いに配慮し、安定した住まいを確保するものではない」と批判しました。
(しんぶん赤旗2025年5月16日付掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。ちょっとこれまでの質問と重なるところも多々あるかと思いますけれども、重大なことだと思いますので、お尋ねをしていきたいというふうに思います。
まず最初に、焦点になっています損害賠償請求権についてお尋ねをしていきたいと思います。
旧区分所有者が損害賠償請求権を持ち続けると今回の改正でなると、十分な補修ができなくなるという懸念に対して、国交省の方は、管理規約の改定で対応するというふうなことで答弁をされておられます。
先日の参考人質疑で、ただ、規約を改定しても、改定前にマンションを売った旧区分所有者を拘束することはできないため、多くの場合、問題は解決しないというふうな意見がございました。
規約の改正前に既にマンションを売却している旧区分所有者には規約の改定で対応できないというのは、法務省もそういう理解でよろしいでしょうか。
竹内政府参考人 お答えいたします。共用部分について生じた損害賠償金の使途等を定める規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたという場合には、その旧区分所有者は規約で定められた義務を負っていないため、管理者が受領した損害賠償金の返金を求めることについても制約を受けないと考えられます。
堀川委員 そういう認識だということです。続いて、国交省の対応として、標準管理規約で対応していくというふうなことなんですが、規約改定の普及状況についてはちょっと飛ばさせていただいて、普及の対応についてお聞きをしていきたいと思います。
この標準管理規約の普及、これまでも大臣はいろいろ答弁されておりますけれども、どう努めていくおつもりかということを最初にお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。先ほど来、共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容につきまして、区分所有法の改正とともに、標準管理規約の改定によって対応をしていくということをるる答弁をさせていただきました。
今回の内容につきましては、あらかじめ規約の定めをしておくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能になり、区分所有者全体の利益につながるものでもあることから、マンションの管理上、影響の大きい事項でもあるというふうに考えております。
各管理組合に対しましても、標準管理規約の改正内容の管理規約への反映が進むよう、先ほど来、様々な手段を用いて周知、普及に取り組んでいきたいということはるる答弁させていただいておりましたけれども、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
堀川委員 先ほど来から、周知徹底に取り組んでいきたいというふうな、決意も含めてあるんですけれども、鳩山委員からも指摘がありました、頑張れないマンションというのが今回大きな課題になっているというふうに思うんですね。
管理規約の改正自体がなかなか自分たちの力量ではできないというふうなマンションであったり、マンション管理士の力をかりるんだというふうなこともあると思うんですけれども、そもそも、このマンション管理士が関わるマンションというのがそんなに多いわけでもないというふうな中で、そういう中で、具体的に、こういう頑張れないマンションの規約改正についてどういうふうに進めていくのか、計画や目標なんかを持っておられるのか、ちょっとそこら辺の措置をお聞きしたいと思います。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。標準管理規約の改正、何らかの形でということで、先ほど来、九割という数字も出させていただきました。その九割が本当に一番最新のものではないではないかとか、いろいろな御指摘はあったところではありますけれども、ただ、いずれにしても、この標準管理規約、できるだけ今回の内容については早く改正をさせていただき、リーフレットの作成、説明会の開催等、また、マンション管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけということで、反映を徹底をしてまいるということは一つございます。
その上で、やはり管理規約への反映状況などを把握をしていくということも大事だと思いますので、マンション総合調査などを活用して実態把握などに取り組むとともに、これは、取り残されるマンションがないように、法務省との緊密な連携の下で、関係者による支援体制も構築をしながら、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
堀川委員 なかなか具体的な対策について答弁がないというふうに思います。なかなか、その実効性が担保されているのかどうかということが本当に懸念として残らざるを得ないような答弁が、先ほど来から繰り返されているというふうに思います。
参考人質疑で、旧区分所有者が損害賠償請求権を持ち続けるというふうなことになってくると、現区分所有者の住まいの権利というのが侵害されかねないというふうな指摘が幾つもあったわけなんですけれども、これは私、重大な指摘だというふうに思うんですね。その対応として、国交省は管理規約で対応していくんだというふうなことをおっしゃるんだけれども、それをどうやって担保するのかというふうな具体的なお答えがないということで、本当に懸念が残るものだということは指摘をしておきたいというふうに思います。
続いて、賃借権の終了請求権の創設についてお伺いをしていきたいと思います。
借地借家法では、賃借権契約を終了させるためには、正当の事由を要件としています。これは、社会的政策でもって借主が保護されるべきという認識でよろしいでしょうか。法務省、お願いします。
竹内政府参考人 お答えいたします。委員御指摘の借地借家法でございますが、二十八条におきまして、建物賃貸借契約の更新拒絶や解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができないこととされております。
このような建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れの規定は、賃貸人側の事情と賃借人側の建物を必要とする事情のほか、諸般の事情を併せてしんしゃくして、両者の利害を総合的に調整するものとして設けられたと承知をしております。
このような規定によって、賃貸人による建物賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れが認められない事例もあると承知をしております。
堀川委員 まあ、でも、あくまでこれは借主の保護というのが主体だというふうに理解をしております。
本改正案では、建て替えの決議があれば、建て替えに参加する区分所有者によって賃貸借の終了を請求することが可能になります。
現行でも、先ほどありましたように、正当の事由があれば、借主に退去を求めることができるようになってはいます。
建て替え決議が上がれば、その決議自体が正当の事由になり得るというふうに私は思うんですけれども、なぜあえて今回のこの賃貸借終了請求権の創設、この規定が必要なのか、説明をお願いいたします。
竹内政府参考人 お答えいたします。現行の区分所有法では、建て替え決議がされた場合でも、直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃借人が合意解除に応じたり、賃貸人による賃貸借契約を更新しない旨の通知又は解約の申入れに正当の事由があると認められたりするなどしない限り、賃貸借は継続をし、賃借人に専有部分の明渡しを求めることができず、そのため、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがございます。
区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず参加しないという場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うこととなり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許容されると考えられるところでございます。
そこで、本改正法案におきましては、建て替え決議があった場合の賃貸借の終了請求の規定を設けることとしたものでございます。
ここでは、賃貸借契約が終了することによる賃借人の損失を補償するために、賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金を支払わなければならないこととするなどしておるところでございます。
堀川委員 建て替えを進めること自体は、私は必要だというふうに思いますし、否定をしません。ただ、やはり賃借人の住まいの権利というのも当然保護されるべきだというふうに思うんです。
今起きている実態として、契約どおり家賃をきちんと払っているにもかかわらず、賃借人に対して正当の事由がないまま立ち退きを強いるというケースが多発しているわけなんです。
賃貸物件をめぐるトラブルの相談などをされている団体から、この間、たくさんの事例を紹介していただきました。
一つだけなんですけれども、都内の事例を紹介させていただきたいんですが、管理事業者やコンサル会社から、正当事由を示されないまま高圧的な態度で立ち退きを数回にわたって要求をされ、心身を病んでしまっているというふうな事例もあります。
この団体の方にお話を聞いていますと、明渡しの正当事由など存在しない明渡し請求が圧倒的で、僅かな立ち退き料で多くの賃借人は泣き寝入りしているのが実態だというふうなお話をされていました。
国交省は、こうした不当な立ち退きの実態、把握しておられるのか。住まいを追われるという不当な実態なんですけれども、国交省としての対応をお聞きをしたいと思います。
中野国務大臣 お答え申し上げます。借地借家法におきましては、賃貸人が建物賃貸借契約の解約を申し入れる際は、賃貸借契約の当事者が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の利用状況、賃貸人が明渡しの条件として財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、解約の申入れをすることができない旨の規律がございます。このような事由が認められない建物賃貸借契約の解約申入れは、基本的に認められないものであるというふうに承知をしております。
法務省からは、訴訟等においては正当事由がないにもかかわらず建物明渡し判決が出されることはなく、これにより、賃借人の利益の保護が図られているものと聞いております。
国土交通省としても、借地借家法の適切な運用により、賃借人の利益の保護が図られることが重要だと考えております。ちょっと個別のケースについてのコメントは差し控えますが、仮に国土交通省に対しまして賃貸物件の明渡しをめぐる紛争等について御相談があった場合には、法務省とも相談をしながら、適切な相談先につなぐなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
堀川委員 これは国交省としても関わらなければならない問題だと思います。
今回の法案の関係では突っ込んでお聞きすることは差し控えますけれども、また引き続き取り上げていきたいというふうに思っております。
今回の改正によって、賃借人は、自分の住まいのことなのに建て替え決議には関与をできないわけですね。賃借権の終了をそのまま受け入れなければならないというふうなことになります。
先ほど御紹介したように、不当で悪質な追い出しのケースというのが絶えないのに、ただでさえ弱い立場の借主の地位をより一層不安定なものにしかねないというふうに思うんですけれども、大臣、そうした認識をお持ちでしょうか。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。区分所有法の改正法案におきましては、賃貸借終了請求がされた場合には、当該請求の六か月後に賃貸借契約が終了するものとされているところ、適切な補償額による金銭的補償を受けるまでは専有部分の明渡しを拒めることとされるなど、賃借人の利益を保護するための規定が設けられているものと法務省から伺っております。
また、賃貸借の終了請求は、借地借家法における正当事由の規律とは異なりまして、マンションを含む区分所有建物の円滑な再生を実現をするという政策目的の下、認められたものでございます。申し上げたような賃借人の利益保護の規定もあることからすれば、賃貸借終了請求の創設が賃借人の地位をより不安定にするおそれがあるという指摘は当たらないものと法務省から聞いているところでございます。
実務的には、建て替えの検討から決議までに平均四年半程度要しているということでございます。当該期間において、様々な意向確認や利害調整などが行われる中で、賃借人の希望等も確認をし、代替居住先の確保に向けた準備を行うということは十分可能であるというふうに考えております。
堀川委員 そうであれば、なぜ六月という期限をあえて設けられたのかということが疑問だというふうに思います。不当な立ち退きが相次いでいる中で、この賃借権の終了請求権というのはやはり危険なものだというふうに私は思います。
続いて、建て替え要件の緩和に伴う少数反対者への保護について最後にお聞きをしていきたいと思います。
今回の改正で、一定の客観的要件が認められる場合は、建て替えの決議要件が五分の四から四分の三に緩和されることになっています。さらに、所有者不明の区分所有者は議決から取り除くことができるというふうな規定も作られました。
次の質問はちょっと飛ばさせていただいて、続いての質問に移りたいんですけれども、建物の老朽化の対策というのはもちろん対応を急がれるものだというふうに思うんですが、同時に、居住者もやはり高齢化をしているというふうな問題があります。
ある事例を紹介をしますと、賃貸マンションで四十年間住み続けた部屋を建て替えが決まったということで退去することになった七十五歳の方、この方は、現役時代の稼ぎもあって、家賃を払うお金というのはあるんだけれども、新居を探そうとしたときに、入居審査まで行った物件でも五回連続で審査落ちになったそうです。結局、退去期限ぎりぎりになって入居先が決まったんだけれども、元々住んでいた町を離れるというふうなことになったそうです。今の賃貸市場では、高齢であるということがリスクとして見られてしまうのが実情です。
補償の話が先ほどあったんですけれども、お金で幾ら補償しても、高齢の方ほど新たな居住先を見つけるというのは本当に今困難になっているわけなんですね。
こうした方々にどう対応していくのか、これは法務省と国交大臣にそれぞれお答えをお願いしたいと思います。
竹内政府参考人 お答えいたします。区分所有法の中では、今回の改正法としては、委員御指摘のように、金銭的な補償を設けているところではございますが、本改正法案全体として、改正後のマンション再生法におきましては、マンション再生事業の施行者や、国及び地方公共団体において、居住の安定確保にもしっかりと取り組むということとしているところでございまして、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出する区分所有者の代替住居の手配についても配慮がされているところでございます。
このように、本改正法案では、建て替え等に反対をいたしました所有者の少数の方々の居住の安定ですとか財産権の保障に適切な配慮がされているものと考えております。
中野国務大臣 御指摘のとおり、マンション再生等の事業を進めるに当たっては、再生等に反対をされる区分所有者や賃借人など転出される方々に対する丁寧な対応、これは極めて重要であると思います。
法律上の措置として、法務省は先ほど金銭的補償を行うという規定のお話をされましたが、マンション再生法におきましても、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項として、売却マンションなどに居住していた区分所有者や賃借人の居住の安定確保に関する取組を位置づけるとともに、地方公共団体や事業の施行者など、これらの取組に努力義務を負うという明記をさせていただきます。
そして、御指摘の高齢者世帯など特に配慮が必要な方々に対しましては、地方公共団体や関係団体と連携をいたしまして、公営住宅等の公的賃貸住宅やセーフティーネット住宅等の活用の促進もございます。居住支援法人による相談対応等の施策もございます。また、リバースモーゲージ型の住宅ローンの提供、住宅金融支援機構が行っております。様々な取組を通じて、居住の安定の確保ということにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
堀川委員 いろいろおっしゃるんですけれども、そうしたセーフティーネット対策がやはりほとんど周知もされていないし普及もされていないというのが地方自治体の実態かというふうに思います。
私は、以前、この問題を質問させていただいたときに、そもそも国交省には、この住宅セーフティーネットによって高齢者などの要配慮者が住居に入居できたかどうか把握する仕組みすらないというふうなことが明らかになっていると思います。
今回の法案、二つの老いに対応するというふうなことですが、マンションの老朽化、高経年化に対しては様々な措置がされているんですけれども、居住者の老いに配慮をして安定した住まいを確保するという視点がやはり欠けているというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
以上で質問を終わります。
堀川委員 私は、日本共産党を代表して、マンションの管理、再生の円滑化等のための改正案に反対の討論を行います。
マンションの老朽化への対応は急がれます。しかし、本法案は、二つの老いへの対策と言いながら、根本的な解決を図るものになっておらず、現居住者の居住の安定を担保する施策が不十分です。必要な施策を講じないままに、老朽化マンションや管理不全マンションを増加させてきた政府の責任は重大です。
第一に、本法案は、建て替え等の決議要件の緩和等を盛り込む一方で、少数反対者への保護がほとんど講じられていません。
これまで政府は、区分所有者法が成立して以来、建て替え決議の要件を緩和してきました。建て替えが待ったなしとなっている老朽化マンションに対しては、その要件緩和もやむを得ないと理解はします。
しかし、その一方で、建て替えの反対少数者の保護の支援策は、ほとんど講じられてきませんでした。本法案は、こうしたこれまでのマンション政策に対する反省もなく、反対少数者を置き去りにしたまま建て替えだけが進められる危険をはらんだものです。
そもそも、老朽化マンションの建て替えが進まない要因の多くは、建て替えによる区分所有者の負担金が重く、合意形成が進まないことにあります。強引な建て替え推進は、区分所有者同士の対立を深め、適切なマンションの建て替えを一層困難にしかねません。
第二は、区分所有建物の共用部分の欠陥について十分な補修ができないものになっているからです。
本法案は、区分所有権が転売により移転しても、損害賠償請求権は旧区分所有者に帰属するとの解釈に基づいています。管理者が区分所有者と旧区分所有者を代理して訴訟が行えるよう改正するとしていますが、旧区分所有者が別段の意思表示を示した場合は、旧区分所有者を代理することはできず、その分の賠償金も得られません。
政府は、あらかじめマンション管理規約を改定することで賠償金を補修に充てられるようにすると言いますが、規約を変更するだけの力量を持っていない管理組合には根本的な改善策にはなりません。今住んでいる区分所有者の生活の安定を侵害しかねないものです。
第三は、本法案が新たに賃借権の終了請求制度を盛り込むものだからです。
現行では、賃借権の終了は、借地借家法の正当事由が必要であり、賃借人の権利が社会的に保護されています。一方で、本法案は、正当事由以外による新たな賃借権消滅手段を創設し、賃借権の終了を容易にします。現行でも横行している賃借人への強引な立ち退き被害を増長するリスクを高めるものです。
なお、立憲民主党及び日本維新の会の修正案については、見解を異にするものであり、賛成できません。
以上、討論を終わります。