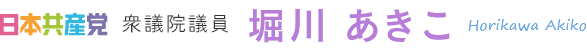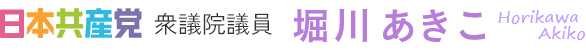国会質問
国会質問


作成中
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。最後の質疑になりますので、最後までおつき合いの方をよろしくお願いします。
今日は、参考人の皆さん、お忙しい中、この委員会に足を運んでいただいて、本当にありがとうございます。そして、日頃からの皆さんの、被災地、現地での支援活動や、あるいは研究活動に心から敬意を表したいというふうに思います。
私からも幾つか皆さんの御意見をお伺いしたいと思っているんですけれども、まず最初に、大野参考人、沢渡参考人、そして栗田参考人にお聞きをしたいと思います。
今回の改正案の中で、一つは、福祉を位置づけるということで、大変重要な視点だと私も受け止めています。そうした関係で、福祉関係者に対して、医療や土木建築工事又は輸送関係者と同様に、罰則を伴う従事命令というものが規定をされるというふうな改正案になっています。
もう一つは、今回、事前登録制度ということで、被災者援護協力団体の登録制度が創設をされるというふうな中で、協力命令の対象とするというふうな改正になっているわけなんですけれども、このことに関して、私も本会議で、ちょっと懸念がありましたので質問をしました。一応、その従事命令に関して、いわば最後の手段として規定されるもので、これまで適用実績はないというふうな大臣答弁があり、登録被災者援護協力団体に対する協力命令については、正当な理由がある場合には従わなくとも登録取消しの対象としないとしておりますというふうな答弁もありました。
実際に支援を担われている皆さん自身のところでの、この従事命令、協力命令の対象にされるということへの受け止めや御意見、お三方からお伺いできればと思います。お願いします。
大野参考人 先ほど栗田さんが話されていたように、お願いから命令にというのが、言葉が表しているんじゃないかなというふうに思います。以上です。
沢渡参考人 繰り返しになりますけれども、NPO、NGOはやはり自分たちの信念に基づいて活動していますし、ボランティアも、自発性というところで、ボランティアは意思に基づいて行動しております。もちろん連携はしていきますけれども、そういったNPO、NGO、ボランティアの特性も尊重していただければと思います。
栗田参考人 そもそも、被災者援護協力団体という呼び方だとか、それから従事命令とか協力命令とか、やはり、私がお聞きしているのは、今の法律でもうどうしようもない部分の言葉を使っているだけだという説明をしていただいていますので、懸念は感じていませんが、ただ、これを正確に読んでいくとどうなのかというふうに疑問を感じる人とか、これは威圧的じゃないかというふうに感じる仲間もいますので、そこは、平易な言葉で、法律用語じゃない言葉でしっかりと御説明をしていただくような機会が必要だというふうには思います。
堀川委員 ありがとうございます。やはり、自発的、自主的な活動を尊重するというふうな視点で、強制力ではなくて、協力を得られるような、そういう環境整備が国として必要ではないかなと改めて思います。
続いての質問なんですけれども、本法案の視点として、応急対策期の対策を強めるということで、重要だというふうに認識しているんですけれども、更にやはり必要だと思うのが、応急対策期を過ぎたとき、様々な支援団体が担っている活動を復興の担い手である地元にどう引き継いでいくのかというふうな視点が私は物すごく重要だというふうに思っています。
先ほどJDFの大野さんから、福祉サービスの提供は、避難所を中心とする支援にとどまらず、長期にわたり広く福祉サービスや事業所を支えることによって、被災地の多くの障害者等に届くものでなければならないというふうなお話をいただきました。ただ、事業所のスタッフの離職者が続いていたり、派遣元の事業所もなかなか人手不足というふうな中で、体制が非常に不安定にならざるを得ないというふうな懸念も出されておりました。
これは阪本さん、沢渡さん、栗田さんにお聞きをしたいんですけれども、応急的支援から長期支援にどうつないでいくのか、これまでの答弁と重なるところもあるかもしれませんけれども、それぞれの問題意識や御意見を聞かせていただけたらと思います。
阪本参考人 ありがとうございます。現在の災害対策は、応急対策、対応と復興がやはりかけ離れているところがあるので、これを将来的には一体的に捉えてできるような仕組みづくりが必要になると思います。以上です。
沢渡参考人 陳述の中でも、地元のNPO・NGO連絡会のような、そういった連絡組織をつくっていくことの重要性というのを話しておりましたけれども、やはり最初のときから、地元のNPO、NGO、そういったリソースにも入ってもらうということが非常に重要なところかなと思います。いきなりトランジションというのは難しいと思うので、最初から、もちろん被災者ではあるとは思うんですけれども、地元の方にも入ってもらうというところが非常に重要な視点かなと思います。
栗田参考人 私も同じで、復興期をちゃんと見据えて、最初からできる限り地元の人たちと一緒にやる、そこを外部支援が心がけるともっと変わってくるんじゃないかなというふうに思います。
堀川委員 ありがとうございます。 被災者にとってみれば、やはり、生活再建までのフェーズというのは地続きで連続的につながっていくというふうなことになると思いますので、応急期、復興期一体化した対策ということで、平時への備えということともつながると思いますけれども、万全な対策が必要ではないかと改めて思います。
続いて、大野参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、先ほどの質問でもありましたが、登録被災者援護協力団体の要件について、最初の意見陳述で、欠格条項について削除するべきというふうな発言がありました。ごもっともな御意見だというふうに思うんです。
この間、東日本大震災から現地で活動を続けてこられたというふうなことなんですが、障害のある方が実際に被災地に入って支援活動を行ってきたというふうなことで、どんな支援がなされているのか、具体的な経験をお聞かせいただきたいということと、加えて、障害者団体の自主的、自発的な活動が被災地でこれからも発揮されるために、もっとこうしたことがあればいいなというふうなこともあれば、是非御意見をお聞かせいただきたいと思います。
大野参考人 まず、JDFの障害のある人の支援スタッフとしての活動についてですけれども、鹿児島県から支援スタッフとして活動された園田さんという方を紹介したいと思います。
この方は、難聴の障害のある方です。JDFのニュースの三号の「やわやわと」のところに掲載がされていますけれども、こういったことを園田さんは書かれています。要約筆記を必要とする難聴者です。専ら支援を受ける側の難聴者がどうして災害ボランティアをと思われたかもしれませんね。そこには二つの狙いがあります。支援する障害者として耳マークストラップを下げながらの前向きさをアピールしたいということ。二つ目に、この活動中、地元の石川県要約筆記者と全国要約筆記研究会の協力を受けて支援活動を展開し、広く要約筆記の認知と普及活動をこれからも継続していく意気込みをアピールすることの二つです。障害のある人もない人も共に助け合う共生社会の実現を目指したいですねということを話されています。
なので、園田さんは、打合せのときはオンラインの遠隔要約筆記を活用したり、日々のコミュニケーションはスマホのアプリ、UDトーク、こういったものを使ったり、一人ずつ話したりする配慮をすることで、支援活動に参加することをされていました。
もう一人は、石川県から参加した土橋さんという方ですけれども、左足に障害があります。この方は、「やわやわと」の三十九号に載っていますけれども、肉体労働は難しいんですけれども車の運転は可能ということで、輪島市町野町の仮設住宅に住んでいる精神障害のある人の通院支援に、二時間かけて行って通院支援を行うということをしてもらっていました。
こういったことも、本人の力が発揮できる場が何なのかということを話し合う中で判断していくということを行っています。
もう一つの自主的な活動の発揮というところでは、石川県の聴覚障害者協会の役員でもある藤平さんという方、この方は、新聞でも報道されましたけれども、支援活動に参加できず、障害当事者の支援団体なのに災害時に置き去りにされた感じがしたというようなことを話されています。対策本部を立ち上げたわけですけれども、県や市に聾者の名簿の提供を求めたけれども断られたということがあったそうです。その結果、奥能登に住む聾者二百六十四人のうち、安否確認ができたのは五十人ほど、二割弱だったということがありました。
なので、この間伝えている被災高齢者等把握事業や被災者見守り・相談支援事業の委託を受けている団体とつながりを持つことで、連携をして障害のある人の支援につながる、つなげていくということが必要だと思っています。
今日の資料の七ページの五十八番のNさんという方はまさにそういう例で、穴水町のレスキューストックヤードが戸別訪問でつながった、寝たきりの男性を、高齢の母親の、仮設住宅生活をされているんですけれども、レスパイト入院の車での送迎をJDFが担う、そういったようなことで、福祉サービスの提供というようなことが連携をする形でできた、そういった例にもなります。以上です。
堀川委員 ありがとうございます。リアルな支援の実態をお聞かせいただきました。私たちも本当に、そのことから学ばなければならないことがたくさんあるというふうに思います。
最後なんですけれども、これはちょっと参考人の皆さん全員にお一言ずついただけたらと思うんですが、今回、災対法等の改正案ということでいろいろ改正の内容があるんですけれども、それぞれの活動の中で、やはりここがまだハードルなんじゃないかとか、あるいはもっとこういうことがあればいいのにというふうなことで、一言ずついただけたらと思います。お願いします。
阪本参考人 ありがとうございます。法制度には規定されているにもかかわらず、実際の現場での運用が難しいことがたくさんあります。ですので、実際に運用できるように持っていくにはどうすればいいのかという点はもっと考えなければいけないと思います。以上です。
大野参考人 誰一人取り残さないという状況がどうなっているのかということなんですけれども、二〇一三年の災害対策基本法の改正で義務化された避難行動要支援者名簿、ここからちょっと問題提起をさせていただきたいと思っています。
愛知県の二〇二四年四月一日の状況ですけれども、避難行動要支援者名簿の全人口に対する割合が、愛知県全体で平均七・三%になっています。名古屋市は一三・四%。一方、三%の自治体は、五十四の自治体のうち二十五自治体、四六%というふうになっています。
何でこんなに違いが生まれるのかというと、自治体ごとに名簿掲載の範囲がばらばらでいいというふうになっていることです。こういったような問題というのを改めて考えていく必要があるなというふうに思います。以上です。
沢渡参考人 今後起こるであろう大きな災害に備えて、やはり日頃から、技術力の向上であるとか担い手の育成に取り組んでいくということが非常に重要だと思います。そういったことが、平時の、顔の見える関係づくりをつくる第一歩だと思いますので、そういったところでの担い手育成に力を入れていきたいと思っています。
栗田参考人 先ほども申し上げましたが、広域避難の課題については非常に課題が多いというふうに思っていますので、ここでも官民連携が実現するような、更なる協力が必要だというふうに考えています。
堀川委員 ありがとうございました。終わります。