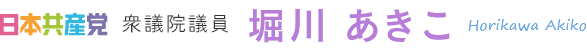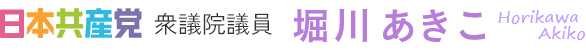国会質問
国会質問


日本共産党の堀川あきこ議員は7日の衆院国土交通委員会で、「マンション関連法」の改定案をめぐり、安定した住まいの確保が不足するなか、富裕層しか手を出せないタワーマンション建設を推進してきた政策を見直し、既存のマンションの修繕を優先する長寿命化対策を抜本的に強化するよう政府に迫りました。
堀川氏が、2002年の同法改定以来のマンション建て替えの実績を聞くと、楠田幹人住宅局長は「事業継続中も含めて472件」と答弁。堀川氏は「建て替えが進んだのは、ごく一部のマンションにとどまっている。建て替えの困難さを認識しながら、一方で同じ時期に大手デベロッパーの要望にこたえて超高層ビル建設のための容積率や利用規制を大幅に緩和してきた」と指摘しました。
堀川氏が2000年以降の規制緩和後、タワマン建設が急増している推移を示したのに対し、中野洋昌国交相は「マンション戸数全体の(タワマンの)占める割合は限定的だ」などと強弁。堀川氏は「規制緩和後にタワマンが急増しているのは否定できない」と批判しました。
堀川氏は、19年の社会資本整備審議会分科会の「マンション規模が大きくなるほどマンション管理にかかる区分所有者の合意形成の困難さが増大する」との指摘を示し、同改定案では有効な対策がまったく講じられていないと指摘。「中低層のマンションの管理不全や老朽化問題すら深刻さが増しているのに、この状況が改善されないままタワマンの建設を進めるのはあまりにも無責任だ」とし、無秩序な大規模開発をやめるべきだと主張しました。
(しんぶん赤旗2025年5月8日掲載)より抜粋
議事録
堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。今回、この法案の前提となる、この間のマンション管理に関する政府の政策とその認識についてお聞きをしていきたいと思います。
区分所有マンションは、区分所有者全員で管理組合をつくり、共同管理することが基本になっています。専門的な知識を持たず、多様な価値観を持つ区分所有者が集団的に建物を管理するということは、困難な面が多いことは当然だと思います。特に高経年マンションでは、区分所有者間での合意形成がより困難となり、管理不全マンションとして近隣住民が危険にさらされるなどの社会問題となっています。
こうしたことを受けての今回の法改正になるというふうに認識をしていますが、政府は、二〇〇〇年のマンション管理適正化推進法や二〇〇二年の区分所有法改正及びマンション建替え円滑化法の制定など、この間も管理適正化や建て替え要件の緩和を行ってきました。当時から、建て替えの困難性やマンション管理の複雑さ、これは認識しておられたというふうに思いますが、いかがでしょうか。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。二〇〇二年の当時の認識ということで、当時におきましても、マンションは、都市における住まいの形態として広く普及をしてきている一方で、老朽化したマンションの急増が見込まれており、都市の再生と良好な居住環境の確保を図る観点から、建て替えの円滑化が重要な課題となっておりました。
また、マンションの管理につきましては、当時の区分所有法では適正な管理を行う上で十分に対応できていないこと等が指摘をされておりました。
このような建て替えの円滑化や管理の適正化に関する指摘などを踏まえまして、二〇〇二年当時、マンション建替え法案や区分所有法及びマンション建替え法の改正法案を政府として提出をし、建て替えの実施の円滑化や管理の充実などを図ったところでございます。
堀川委員 資料の一、二を御覧いただきたいんですけれども、ただいま大臣から答弁もあったように、二〇〇二年のマンション建替え円滑化法案の提案理由で、当時の扇千景国交大臣は、今後、老朽化したマンションが急増することが見込まれており、マンションの建て替えの円滑化が重要な課題となっていると述べておられます。また、同じ年の区分所有法及びマンション建替え円滑化法改正案の提案理由については、現行の法で適正な管理を行う上で十分に対応できないことが指摘されておりますというふうな表明がなされておりました。
こうした認識の下、対策が講じられてきたというふうなことですが、マンションの建て替えの実績はどうなっているでしょうか。国交省、お願いします。
楠田政府参考人 お答えいたします。これまでのマンションの建て替えなどの実績につきましては、事業継続中の案件なども含めまして四百七十二件となっております。
堀川委員 結局、建て替えが進んだのは、ごく一部のマンションにとどまっているというふうなことだと思います。
建て替えの困難さを認識しながら、一方で、同じ時期に、大手ディベロッパーの要望に応えて、超高層ビル建設のための容積率や利用規制を大幅に緩和をしてこられました。二〇〇〇年には容積率の移転、売買を可能にする特例容積率適用区域制度を創設をし、二〇〇二年に都市再生特別措置法、二〇一三年には国家戦略特区法を制定をし、都市部における大規模開発、これが可能になってきました。
一連の制度改正、いわゆる規制緩和が超高層マンション、タワマンの建設増加につながっているというふうに考えていますが、大臣の見解をお聞かせください。
中野国務大臣 お答え申し上げます。我が国の活力の源泉でもあります都市の魅力や国際競争力を高めることなどを目的としまして、民間事業者による都市整備を進めていくということについては重要なことであるというふうに考えております。
そして、長期的な観点に立ったまちづくりに際しましては、様々な都市計画制度などを活用するなど、自治体がそれぞれの将来像に合わせて創意工夫を図りながら推進をしているものと考えております。
その中では、マンションの新規の立地を制限をしている自治体も見受けられます。例えば、神戸市では、商業や業務機能の集積とバランスの取れた都心の居住を誘導するため、マンションを含めた住宅の建築等が制限をされているところでもございます。
いずれにしましても、マンションの立地を含めまして、まちづくりにつきましては、地域の実情を踏まえて、自治体が適切に判断をし、実施をすべきものであると考えております。各地方自治体に都市計画制度の適切な運用を促してまいりたいというふうに考えております。
堀川委員 お答えになっていないかと思うんですけれども。
資料三に、タワマン建設数の推移を示しております。二〇〇〇年代の規制緩和後にタワーマンションの建設が急増をしているわけですね。
規制緩和はタワマンの建設に関係ないと言えないというふうに思うんですが、大臣、このことを認めますか。もう一度答弁をお願いします。
中野国務大臣 例えばで申しますと、都市再生特別措置法により大臣認定をされた優良な民間都市開発プロジェクトにより供給をされた分譲住戸数につきましては、例えば、東京都内のマンション販売の戸数に占める割合は、令和元年から令和五年までの五年間で見ても平均で二・五%程度ということで、非常に低い数字でございます。全体的なマンション建設戸数への影響というのは限定的ではないかというふうに考えておる次第であります。
堀川委員 規制緩和後にタワマンが急増しているのは事実なんですね。幾ら否定されても、このことは否定できないというふうに思います。
そして、タワーマンションの老朽化や管理不全も避けられない問題になっているわけです。
二〇一九年、社会資本整備審議会住宅宅地分科会マンション政策小委員会の取りまとめにおいても、マンションの大規模化について、マンション規模が大きくなるほどマンション管理に係る区分所有者の合意形成の困難さが増大する傾向にあるというふうに指摘をされています。
こうした指摘にどう応えるのか、お答えいただきたいと思います。
中野国務大臣 令和五年度マンション総合調査によりますと、超高層マンションと一般のマンションとで、総会の参加割合や理事会の開催の状況、必要な修繕積立金の積立状況などに大きな違いはないものと承知をしております。
また、同調査によりますと、超高層マンションと一般のマンションとで、直近の大規模修繕工事に要した床面積当たりの費用にも大きな違いはないという状況であります。
他方で、超高層マンションは特有の設備を有しているという面もあることから、現在、修繕項目などに関する更なる実態調査を進めているところでもあります。その結果も踏まえまして、ガイドラインの見直しなど必要な取組を行ってまいります。
本改正法案では、修繕等の日常の管理行為については集会出席者の多数決での決議を可能とするなど、更なる管理の円滑化に向けた措置を講じることとしておりますので、これらの措置も有効に活用しながら、引き続き、超高層マンションも含めたマンションの管理の適正化をしっかり推進してまいります。
堀川委員 もう一つ指摘を紹介したいと思うんですけれども、齊藤広子横浜市立大学教授のタワーマンションを対象にした調査によりますと、六割のマンションで分譲時に設定された修繕積立金を見直して、約八割のマンションで段階的な値上げが予定されているにもかかわらず、三割のマンションで大規模修繕の費用が足りない可能性というのが示唆をされています。
タワーマンションが修繕費不足に陥って管理不全に陥ってしまえば、周囲への影響は甚大だと考えますが、どんどん増え続けるタワマンの管理、どうするおつもりなのか、お聞かせください。
中野国務大臣 お答え申し上げます。先ほど答弁申し上げました調査等も踏まえて、超高層マンションと一般マンションとで、総会の参加割合あるいは理事会の開催状況、そして必要な修繕積立金の積立状況など、管理に関する状況に大きな違いはないというふうに承知をしております。
したがって、様々、規制緩和等を行ってきた結果、こうした建設が促進をされているのではないかという御指摘もございましたが、こうした規制緩和の妥当性の判断に影響を与えるような状況にはないということを認識をしております。
他方で、マンションは国民の一割以上が居住をする重要な居住形態であります。建物と区分所有者の二つの老いが進行し、外壁の剥落等の危険や集会決議の困難化などの課題が顕在化しておりますので、こうした状況も踏まえて、今回、改正法案を提出をさせていただきました。
超高層マンションも含めたマンションの適正な管理や円滑な再生に向けて、引き続きしっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。
堀川委員 その認識で、果たしてこのままでいいのかということは改めて指摘をしておきたいというふうに思います。
六番目の質問は指摘にとどめておきたいのですが、やはり法案では有効な対策が全く講じられていないというふうに思うんですね。中低層のマンションの管理不全や老朽化問題すら深刻さを増しています。この状況が改善されないまま、管理や建て替えがより困難なタワマンの建設を進めるのは余りにも無責任だと言わなければなりません。無秩序な大規模開発はやめるべきだというふうなことを指摘をしておきたいと思います。
続いて、この間のマンションの管理政策の無計画さを指摘してきたんですけれども、以前、住まいを確保することが困難な方々、住宅確保要配慮者に関する質問もさせていただきました。今後こうした方々が増えていくということは国交省も認めておられますが、安定した住まいの確保のための政策が、住宅セーフティーネットでもマンション居住でもやはり大きく不足しているとしか言いようがないと思うんですね。富裕層しか手が出せないようなタワマン建設を推進してきた政府の政策は見直すべきだというふうに強調をしたいと思います。
マンションは、適切な管理がなされれば百年はもつというふうに言われています。これまでの政策を見直して、新たにタワマンばかりを建てるのではなくて、既存のマンションの修繕を優先する長寿命化政策を抜本的に強化すべきだというふうに考えますが、大臣の見解をお聞かせください。
中野国務大臣 お答えを申し上げます。規制緩和の妥当性がどうだったのかということにつきましては先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、長寿命化のための政策を強化していくべきという指摘でございます。
マンションについては、修繕積立金の積立てと大規模修繕工事の実施を適切に行い、ストックの長寿命化と良好な居住環境の維持を図るということは重要でございます。
このため、修繕積立金や修繕計画に関するガイドラインの作成、大規模修繕工事を実施した場合の固定資産税の減額、大規模修繕工事の実施に対する補助、住宅金融支援機構による融資など、支援措置を講じているところでございます。
さらに、本改正法案では、長寿命化に向けた取組がより一層円滑に進むように、管理計画の認定対象に新築マンションを追加をし、修繕に係る決議を集会出席者による多数決とするほか、民間団体の登録制度を創設をし、地域全体で管理組合を支援する体制を構築するなどの措置を講じることとしております。
引き続き、税制、予算、金融など、あらゆる政策ツールを活用して、大規模修繕工事の計画的な実施などの、マンションの長寿命化に向けた取組を推進してまいりたいと思います。
堀川委員 税制について説明されましたけれども、その税制の活用の要件として、管理計画認定マンションであるということが要件に挙がっていると思います。ただ、先ほど来からも指摘がありますように、その認定を取得している割合というのがかなり低くなっているというのが現状です。
二つの老いが深刻化しているマンションではこうした支援制度を活用する力さえないというのが実態だと思いますが、今後も大規模に発生する老朽化マンションの長寿命化にそれらの施策で対応し得るのか、そうお考えなのか、最後、お聞かせください。
中野国務大臣 マンションの維持管理は非常に重要であります。マンションは区分所有者の私有財産でございまして、まず区分所有者に管理の責務があることを認識をいただき、適切な維持管理に努めていただくということは大切でございますが、一方で、区分所有形態という特殊性、あるいは、管理不全となった場合、大変に周辺に影響が大きいということで、地方公共団体等と連携をして、適正な維持管理等に取り組む管理組合をしっかり支援をしていくということが重要であると考えております。
先ほど来、ガイドラインの整備などのソフト支援、予算、税制特例などの支援などを講じてきたということを申し上げましたが、本改正法案では、地方公共団体が、マンションの管理状況などを把握し、再生などの働きかけを能動的に行いやすくなるように、報告徴収などを行える措置を講じるほか、マンションの管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設をして、地域全体で管理組合の活動を支援する体制の構築を進めていくこととしております。
こうした地方公共団体あるいは関係団体と連携をして、管理組合がマンションの管理をめぐる様々な課題に適切に対処できるよう、丁寧な支援に努めてまいりたいと思います。
堀川委員 地方公共団体と連携してというふうなお話でした。
私、地元京都ですけれども、京都市が、管理不全マンションを出さないようにということでかなり頑張っておられます。しかし、その体制は、たった四人で、しかも、ほかの任務と兼務ということなんですね。なかなか行き届かないという実態があると思います。質問を終わりますが、引き続きこの点については議論をしていきたいと思います。終わります。ありがとうございます。